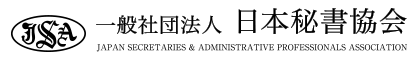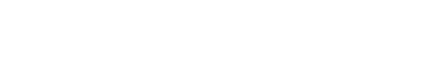政府は今年6月、「国民を詐欺から守るための総合対策」を策定しました。その背景には、巧妙化・多様化する犯罪手口と、詐欺被害の急増があります。「特殊詐欺」「SNS型投資・ロマンス詐欺」「フィッシング詐欺」などの被害件数と被害額は一昨年から増加傾向にあります。
最近の深刻な手口として「警察や検察を名乗る脅迫型詐欺」があります。犯人は警察官や検察官になりすまし、「あなたの口座が犯罪に利用されています」と電話やLINEで不安を煽り、資産状況を聞き出して新たな口座を 開設させ、全財産を振り込ませる手口です。これにより資産は暗号資産などに変換され、被害者が詐欺に気づく頃には口座が空となり、被害者のその後の人生に深刻な影響をもたらします。
警視庁の特殊詐欺対策ページでは犯罪事例を解説する動画が掲載されており、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)には相談窓口も設置されています。少しでも異変を感じた際は、これらの情報を参考にしたり、相談窓口を利用することが推奨されます。
以前は詐欺のターゲットは高齢者や金融リテラシー弱者、借金や孤独感を抱える人、ギャンブル好きや情報 セキュリティ弱者が中心でしたが、現在では「インターネットにつながるすべての人」が標的です。その背景にはスマホの普及があります。スマホの高機能化と低価格化によって生活必需品となり、見知らぬ人とつながる機会が増えました。さらに、「スマホ依存症」による判断力の低下や、AIによる検索履歴・購買履歴の分析に基づく興味関連のプッシュ通知が新たな接触を生むことも影響しています。また、SNSの普及によって「簡単バイト」と称する闇バイトに応募し、銀行口座を開設させられ、その口座が特殊詐欺に悪用されるケースが増えています。このような口座悪用が脅迫材料となり、さらなる犯罪に加担させられる事例も見られます。
法人が直面するリスクには「サイバーリスク」と「マネーロンダリング」があります。個人ができる対策としては、標的型メール対策訓練への参加、怪しいメールの慎重な取り扱い、異変時の相談が重要です。また、個人PCを会社ネットワークで使用しないことや、仕事とプライベートのファイアウォールを維持することも必要です。
こうした被害を防ぐには、官民が一体となって連携することが重要です。特に個人レベルでは、家族(特に離れて暮らす高齢者や親子間)、学校、職場、地域でのコミュニケーションが鍵となります。「うまい話はない」「絶対に儲かる投資は存在しない」「楽して儲けることはリスクが高すぎる」という意識をしっかり共有し、浸透させることが求められます。異変を感じたときは、迷わず相談することが大切です。また、日頃からコミュニケーションを重ね、相談しやすい環境を整え、周囲が異変に気づける関係性を築くことも必要です。
今回、様々なケースの詐欺と対策について総合的に知ることができ、大変貴重な機会となりました。自分自身や家族を金融犯罪から守るためにも、早速、学んだ対策を実践したいと存じます。
詳細
| 日時 | 2024年10月30日(水) |
|---|---|
| 会場 | ハイブリッド開催 |
講師プロフィール
遠藤 洋 氏(GMOあおぞらネット銀行株式会社 AML企画室)
1988年3月 東京都立大学工学部卒、1988年4月 新日本証券株式会社(現・みずほ証券)入社
ソニー銀行、PayPay銀行、メルカリ・メルペイ、現職にてAML(マネーロンダリング防止)・不正対策に従事