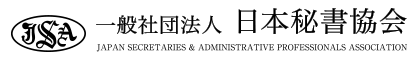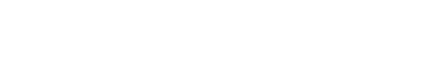今回のテーマは、渋沢栄一と仏蘭西ですが、私が安全保障研究家ということで、危機管理について、有事の際の対応の話のリクエストがありましたので、はじめに危機管理の話を少し致します。もっとも、本来「安全保障」と「危機管理」は別の概念で、私は現在、安全保障をテーマにしていますが、危機管理も研究したことがあるので、リクエストにお応えしたく思います。
有事には、戦争だけでなく、テロや感染症、自然災害等、様々な事象がありますが、今回はその中でも、私たちにとって身近な地震を例に挙げたいと思います。私達が経験した異なる3つの地震を取り上げて考えてみましょう。
1つ目は30年前(1995年1月17日)に起きた阪神淡路大震災です。この地震は直下型で、特に家屋や家具の倒壊で多くの犠牲者が出ました。2つ目は、2011年3月11日に起きた東日本大震災です。大津波によって町は破壊され、甚大な被害、多数の命が奪われ、今だに行方不明者もいます。3つ目が、皆様の記憶に新しい昨年(2024年)1月1日の能登半島地震、これは津波も発生しましたが、家屋の倒壊が主な原因で多くの人が犠牲になりました。
これらの震災から学んだことは「臨機応変」という言葉です。日頃から防災用品の準備や訓練は大切ですが、いざという時に、命を守るにはどうしたら良いかということです。
例えば、能登半島沖地震では、警察官の方が話していた事が忘れられません。地震の揺れを突然感じた警察官は家から飛び出たのですが、家の中から息子が「お父さん、いつもの訓練通り机の下にいるよ。」と声がした直後、家屋が倒壊し、それが息子さんの最期の声になってしまったと言う涙ながらのお話です。
また、東日本大震災の際は、小学生らが先生の指示に従い避難したところ、避難先で並んでいる所を津波が襲い悲劇となりました。その避難の途中、たまたま後ろの方にいた数人が「高台に逃げろ」という声を聞いて列から離れ難を逃れました。日本人は訓練通りに行動することにたけていますが、緊急時には訓練だけでなく直感とサバイバル精神が求められます。自分の命を守れなければ、他の人を助けることもできません。
さらに、先人の知恵も重要です。東日本大震災の丁度400年前に同様の大津波が起きています。その時に立てられたお地蔵さんより後ろに住んでいた人たちは津波から助かり、逆にそれより前にあった家々は流されました。このように、歴史を学び、先人の知恵を活かすことも大切です。
結論として、危機管理というのは、マニュアルも大事ですが、いざとなった時は臨機応変に、命を守るために行動することを、頭の隅に置いておいてください。
■渋沢栄一と仏蘭西
それでは、今回のテーマ「渋沢栄一と仏蘭西」についてお話しします。渋沢栄一は、昨年7月からの新1万円札の顔として知られていますが、皆さんが思い描く「渋沢栄一像」といえば、実業家としての姿が強いかもしれませんが、本日は、渋沢栄一の別の側面も見て行きたいと思います。
■渋沢栄一の出身地と彼の精神
渋沢栄一は埼玉県深谷市の出身で、深谷駅前には彼の像が立っています。深谷駅は小さな駅ですが、非常に立派で、実は東京駅の丸の内駅舎を模して建てられています。なぜなら、渋沢栄一は東京駅の建設にも関わり、円滑に進めるためにサポートをしたからです。これが、1万円札の裏面に東京駅の写真が使われている理由です。
また、深谷市には「願誓寺」というお寺があります。願誓寺を1824年に建立したのは中島丹助という人物で、彼は近江商人から僧侶に転身しました。近江商人と言えば、その精神を表わす言葉として、皆様は「三方よし」を思い浮かばれるかと思います。すなわち、売り手と買い手だけでなく、世間全体の利益を考えた商売です。渋沢栄一も、この精神を大切にしていたと思います。社会全体への貢献を重視していました。このような考え方は、現代のSDGsやCSR(企業の社会的責任)の考え方にも通じています。日本では江戸時代から、そのような考え方があったということを私たちは誇りに思ってよいでしょう。
■渋沢栄一とフランスとのつながり
さて、なぜ今回は「渋沢栄一と仏蘭西」なのかというと、実は渋沢栄一は1867年にフランスのパリ万博に参加するため、初めてフランスに渡りました。これは日本がアジアで初めて招待された万博で、渋沢は徳川慶喜の依頼で、弟の徳川昭武に随行しフランスへ行きました。当時、渋沢は27歳で、役割は主に会計係でした。つまり、彼が中心人物だったわけではありませんが、この経験が彼の人生に大きな影響を与えました。
パリ万博では特に商人の清水卯三郎が出展したお茶室が注目を集めました。また芸者を連れて行き、その美しい立ち振る舞いにフランスの紳士たちは感動したと言われています。このような文化交流を通じて、日本が世界に誇れる文化を持っていることを西洋の人々も認識できました。画家ゴッホが浮世絵に影響を受けたような「ジャポニズム」も、このパリ万博がきっかけだったと言われています。
ヘミングウェイの言葉を借りれば、「もし幸運にも、若者の頃、パリで暮らすことができたなら、その後の人生をどこで過ごそうとも、パリはついてくる。」の通り、渋沢栄一は27歳で初めての外国に長く滞在し、彼にもずっとパリがついてきたと思います。
■フランス滞在後の影響
フランスでの経験が渋沢栄一に与えた影響は大きく、その後、彼は国際的な視野を持つようになりました。1924年には、日仏会館の設立に携わり、フランスのポール・クローデル大使と深い親交を結びました。クローデルは、関東大震災の後に「日本人は貧しい、しかし高貴である。」と言っています。この言葉は、日本人の冷静さと他人を思いやる精神に感銘を受けたクローデルの深い敬意を表しています。渋沢栄一は、このような人物と親交を結び、さらに国際的なつながりを深めました。
■「渋沢栄一と仏蘭西」とその遺産
明治以降、フランスから日本にもたらされたものは沢山あります。一つは、西洋の技術で、鉄道や港湾等、日本のインフラを整備するのに役立ちました。日本の誇る西陣織物等が発展するにもフランスの技術が貢献しました。二つ目は、貨幣制度、株式市場、公債発行等、西洋の制度です。渋沢は、会計係として、徳川昭武の滞在費を工面するため、苦労しながら西洋の経済制度を目の当たりに学んだようです。三つ目が、フランスにおける自由平等の精神です。官尊民卑でない自由な人間関係に、渋沢は感銘を受けたと言われています。
そして晩年の渋沢栄一は、社会貢献を重視し、養育院の院長として恵まれない子どもたちの教育にも携わりました。渋沢は、古稀(70歳)の時に500余りの企業、600近い団体の役員を辞任し、91歳で亡くなるまでの約20年間は養育院の仕事に専念します。彼の最期の講話は、1931年6月に養育院で行ったもので、国家・社会に尽すことは、「その身自身の上にも幸福が来る」と、日本の将来を担う子供達に語っています。
渋沢栄一は、「肩書き」で人を見る人ではありませんでした。立派な渋沢邸には、世界の著名人も招かれましたが、普通の女学生も招かれ同様のおもてなしを受けました。損得や肩書ではない人間関係を大事にした渋沢の人物像が窺われます。
谷中霊園には、徳川慶喜が眠っていますが、それを見つめるように渋沢栄一のお墓があります。渋沢は、最期の最期まで、そして永遠に将軍に「忠義」を忘れない武士道精神を有した人だったのでしょう。
今回のご講話を伺い、改めて渋沢栄一氏は、現代の私たちにも多くの教訓を与えており、彼の社会貢献の精神や平等の理念は、今後の社会においても大切にしていきたいと思いました。<月例会委員>
詳細
| 日時 | 2025年3月21日(金)19:00~20:30 |
|---|---|
| 会場 | ハイブリッド開催 |
講師プロフィール
鈴木 くにこ 氏 (外交・安全保障研究家)
学習院女子高等科時代、ロータリー青少年交換計画で渡仏、バカロレア取得。慶應義塾大学法学部政治学科を首席卒業。外務省入省。国際報道課及び在仏日本大使館勤務。トゥルーズ第一大学政治学前期博士号(DEA)及びヨーロピアン大学経営学修士号(MBA)取得。慶應義塾大学法学研究科後期博士課程を単位取得退学。
国会議員(中山太郎元外務大臣)秘書や東京大学特任助教授、NPO法人岡崎研究所主任研究員等を経て、現職。
著書に、『オリンピックと日本人の心』「内外出版」『歴代首相物語(共著、新書館)『日本の外交政策決定要因』(共著、PHP研究所)等。